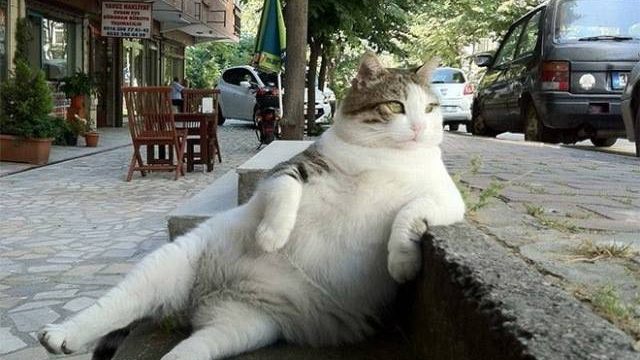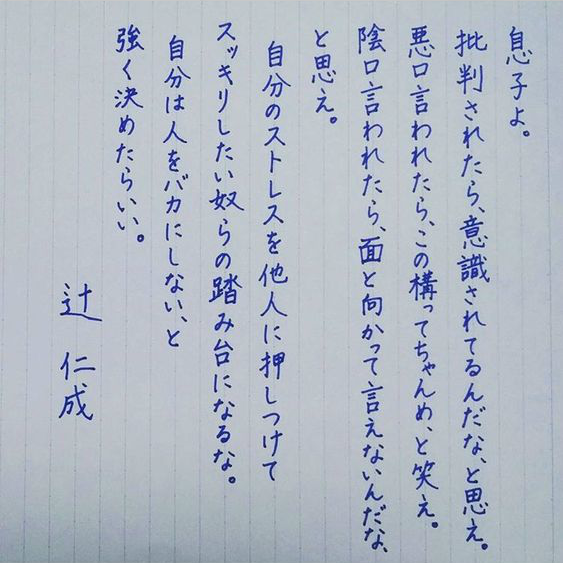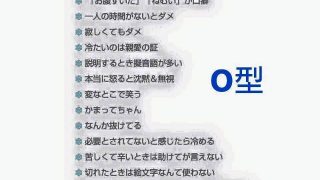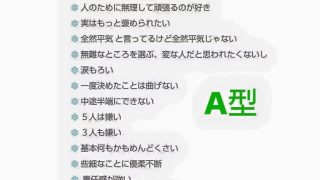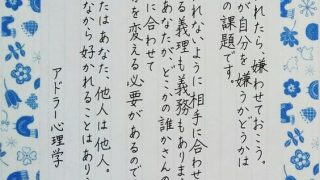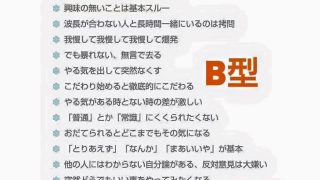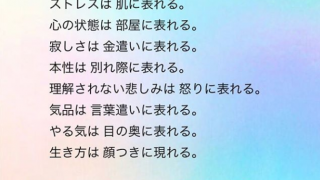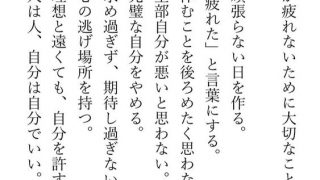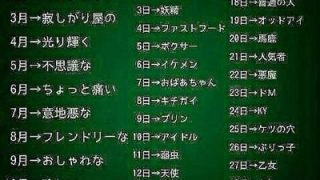【 働かずして、金銭を騙す人の心理 】

1.経済的困窮
→ 生活苦や借金など、経済的に追い詰められている場合、藁にもすがる思いで詐欺に手を染めることがあります。
2.ギャンブル依存症
→ ギャンブルで負けたお金を取り戻そうとしたり、ギャンブル資金を得るために詐欺を働くことがあります。
3.薬物依存症
→ 薬物購入資金を得るために、正常な判断力を失い、詐欺に手を染めることがあります。
4.承認要求
→ 他人を騙すことで優越感や達成感を得ようとしたり、周囲の注目を集めようとすることがあります。
5.自己顕示欲
→ 巧みな話術や嘘で他人を操ることに快感を覚え、自己の能力を誇示しようとすることがあります。
6.劣等感
→ 社会的に成功している人や裕福な人への妬みや恨みを抱え、他人を陥れることで優位に立とうとすることがあります。
7.孤独感
→ 人との繋がりを求め、親切心を装って近づき、信頼関係を築いた上で金銭を騙し取ることがあります。
8.快楽主義
→ 労働をせずに楽をしてお金を得たいという要求が強く、論理感や道徳観が欠如していることがあります。
9.衝動性
→ 計画性がなく、衝動的に行動し、結果を考えずに詐欺に手を染めることがあります。
10.共感性の欠如
→ 他人の痛みや苦しみを理解する能力が低く、罪悪感を感じにくいことがあります。
11.責任転稼
→ 自分も行為を正当化し、責任を他人に転稼する傾向があります。
12.認知の歪み
→ 現実を歪曲して認識し、自分の行為を合理化する傾向があります。
13.計画性
→ 緻密な計画を立て、周到な準備をして詐欺を実行する場合があります。
14.演技性
→ 巧みな話術や演出力で他人を信用させ、騙すことに長けている場合があります。
15.カリスマ性
→ 魅力的な人物像を演出し、他人を惹きつけ、信用させる場合があります。
16.権威性
→ 権威のある立場や専門家を装い、他人を信用させ、騙す場合があります。
17.集団心理
→ 仲間と共謀し、役割分担をして組織的に詐欺を行う場合があります。
18.情報操作
→ SNSやインタネットなどを利用し、偽情報を流布し、他人を騙す場合があります。
19.心理的マインドコントロール
→ 相手の心理を巧みに操り、抵抗できない状態にして騙す場合があります。
20.過去のトラウマ
→ 過去のトラウマや虐待経験などが、他人を攻撃したり、利用したりする行動に繋がることがあります。
これらの心理的要因は複雑な絡み合い、単独で存在するとは限りません。
詐欺被害に遭わないためには、これらの心理を理解し、警戒心を持つ事が重要です。