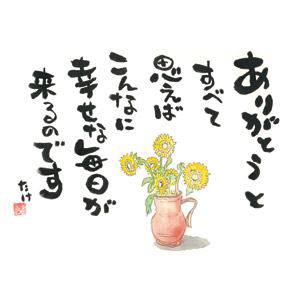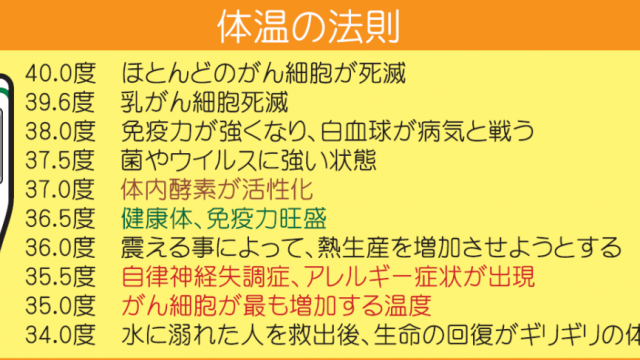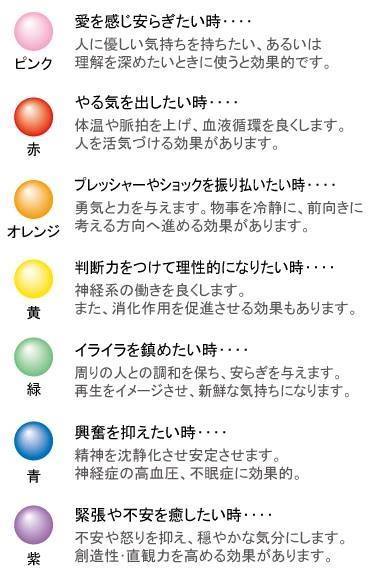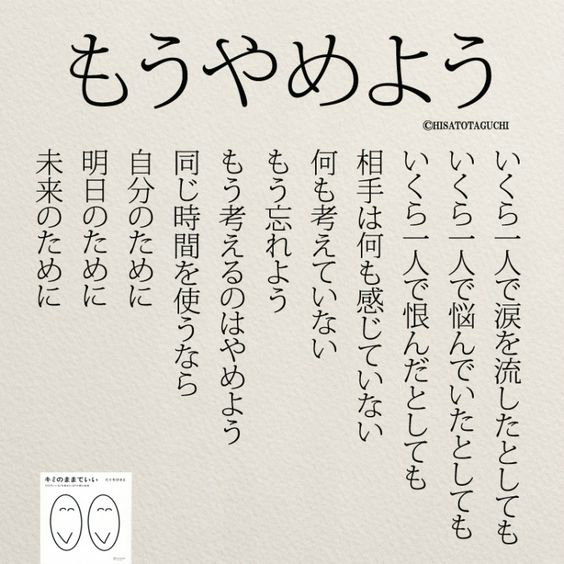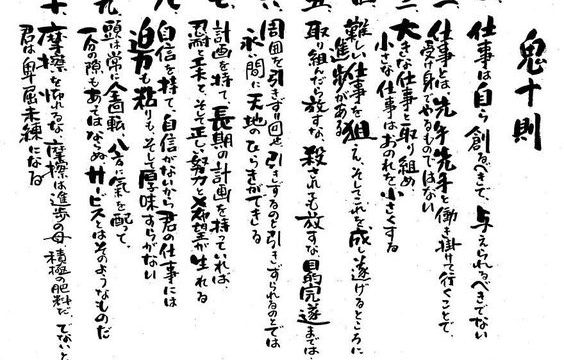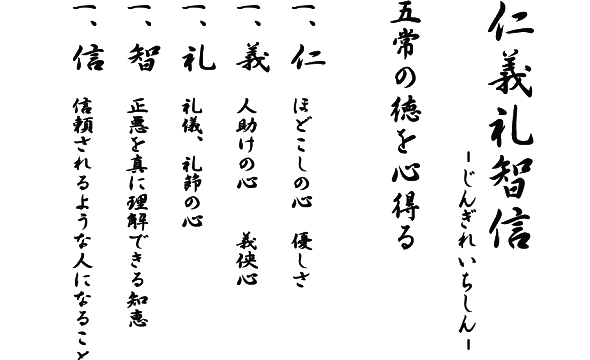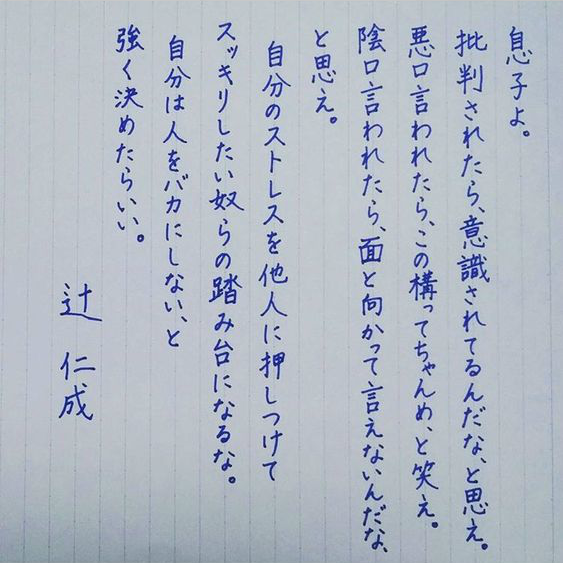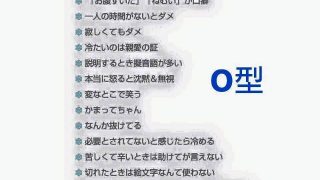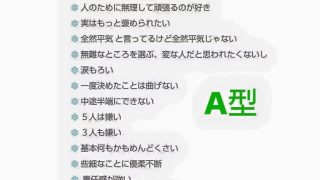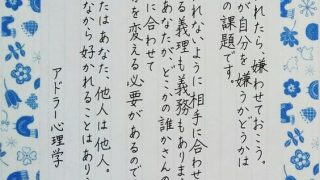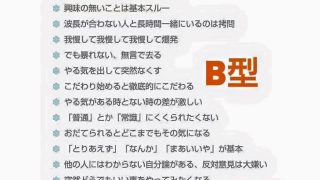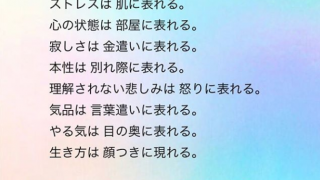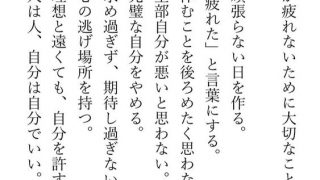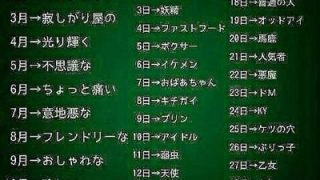【 静かに消えかけている日本の風習 】

日本にはかつて日常の中に根付いた多くの風習や文化がありましたが、時代の変化とともに静かに姿を消しつつあるものも少なくありません。
1.回覧板(かいらんばん)
→ かつては地域の連絡手段として重要だった回覧板も、SNSの普及により使用頻度が激減。特に若い世代には存在すら知らていないことも。
2.年始の挨拶まわり
→ 新年に親戚やご近所へ直接足を運んで挨拶する風習も、コロナ禍以降さらに減少。今はLINEや年賀状、オンラインで済ませる人が多数。
3.井戸端会議
→ 近所の人たちが井戸や路地裏、公園などでおしゃべりする「井戸端会議」も、核家族化や防犯意識の高まりで減少。地域のつながりも希薄に。
4.お中元・お歳暮の手渡し
→ 季節の挨拶として贈るお中元・お歳暮も、百貨店やネット配送の普及で「直接渡す」文化はほとんど見られなくなってきています。
5.床の間・掛け軸のある和室
→ 日本家屋に必ずあった床の間も、マンション暮らしの増加により見かけることが減少。茶道や季節の設え(しつらえ)文化も希薄に。
6.町内会や自治会の共同作業
→ 地域の清掃やお祭りなど、地域のコミュニティでの活動参加が減ってきており、若い世代の関心も低下。形式的に続いているところも多い。
7.和装(特に日常の着物)
→ かつては日常的に着られていた着物も、今は冠婚葬祭や観光地でのレンタル利用がほとんど。自宅で着付けできる人も減少。
8.「ご近所づきあい」や「おすそ分け」
炊き込みご飯やお裾分けを持ってご近所に配る文化も、プライバシー意識の高まりや共稼ぎ世帯の増加で激減。
9.正月の羽根つき・凧揚げ
かつてはお正月に当たり前に見られた風景も、今ではほとんど見かけない。公園や空き地の減少、安全面の問題も一因。
10.送り火・迎え火(お盆の風習)
→ 都市部ではマンション住まいが増え、玄関先で火を焚いてご先祖を迎えるといったお盆の風習も難しくなり、消えつつある。